会議室は本当に使われている?オフィス稼働率を可視化する分析と改善策— ファシリティマネジメントに活かす実践ノウハウ
コラム
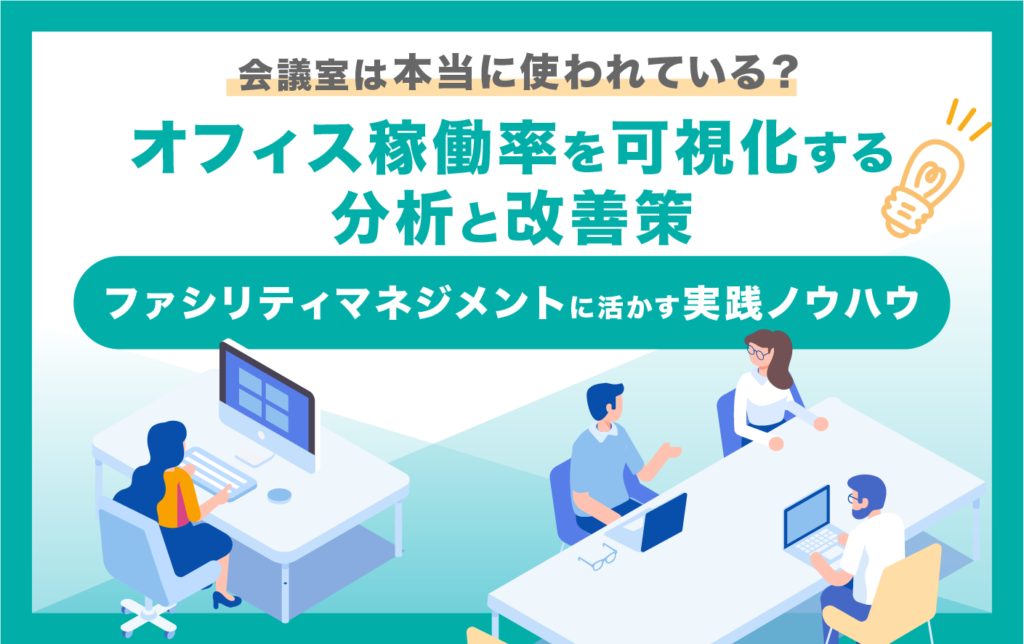
オフィスの見直しや移転を検討する際、見逃されがちなのが「会議室の稼働率」です。見た目には使われているようでも、実際には空予約が多かったり、使い勝手の悪さで形骸化していたりするケースも。
今回は、そんな“見えない非効率”を可視化するための考え方と方法を、実際の業務に落とし込めるように整理してご紹介します。
オフィス稼働率を把握すべき理由とは?
会議室をはじめとしたスペースの活用状況を定量的に把握することは、企業の生産性やコストに直結する大切な取り組みです。このセクションでは、なぜ「稼働率」が注目されているのか、その背景と課題について見ていきましょう。
なぜ今、稼働率分析が求められているのか
ABWが普及する中で、オフィスの“使い方”が大きく変わりました。にもかかわらず、多くの企業では旧来のスペース配分をそのまま維持しており、結果として「使われていない空間」が発生しています。
特に会議室は“見た目の稼働率”が高くても、実際には空予約やキャンセルによる非稼働時間が多く含まれていることも。こうした実態を把握せずにオフィス設計や移転を進めると、余計なコストや働きづらさを招きかねません。
空予約や使用実態のズレが生む課題
たとえば、常に「予約済み」の会議室があると、「うちの会議室は足りていない」と誤解されがちです。
しかし蓋を開けてみると、実際には誰も利用していない時間帯が多くあった…ということも珍しくありません。
これは予約システムの運用が形式的になっている証拠でもあり、現場の運用改善が必要なサインでもあります。空予約のまま放置される時間が積み重なると、社員の不満や非効率だけでなく、新しいオフィス設計にも悪影響を及ぼすことになるのです。
現状把握に必要な「稼働率」の視点と測り方
会議室の「稼働率を見たい」と思っても、実際にどのように測ればいいのか戸惑う方は多いはず。この章では、稼働率を正しく捉えるために必要な考え方と具体的な指標について紹介します。
「稼働率」とは何か?よくある誤解を整理
稼働率を誤って理解しがちなのが、先述のように「予約されている時間=使用されている時間」とみなしてしまうことです。本来の稼働率は、会議室が実際に利用されていた時間の割合を指します。
たとえば、予約されていても無断キャンセルされた場合、それは“稼働”とは言えません。予約と実使用には乖離があり、短時間の利用や非公式な使用は記録されないことも。だからこそ、“使ったかどうか”の正確な把握が重要です。
オフィス稼働率を可視化するための3つの指標(使用率・空予約率・利用頻度)
稼働率分析の際は、以下の3つの視点を組み合わせるのが効果的です。
- 使用率:予約された会議室のうち、実際に使われた時間の割合。
- 空予約率:予約されたものの、実際には使われなかった割合。
- 利用頻度:部屋単位での使用回数や、曜日・時間帯ごとの偏り。
これらを併せて分析することで、「人気の部屋が偏って予約されている」「午後の会議室は全体的に使われていない」といった傾向が見えてきます。
ファシリティマネジメントで注目される会議室の稼働率

ファシリティマネジメントとは、企業の資産や設備を最大限に活用する考え方です。その観点から見ると、会議室の稼働率はまさに改善対象の宝庫。このセクションでは、稼働実態をどう読み解くか、考えてみましょう。
会議室は“予約されている”だけでは不十分
予約表がびっしり埋まっているからといって、必ずしも会議室が不足しているとは限りません。
たとえば「1時間の会議」として予約されていても、実際に使われたのは15分だけということも。長時間予約が常態化している場合や、直前のキャンセルが放置されるケースも含め、“見た目の稼働率”と“実際の利用実態”のギャップは想像以上に大きいのです。
ファシリティマネジメントでは、こうした非効率な稼働状況を数値化し、リソースの最適化に活かします。
空予約や無断キャンセルの実態とインパクト
ある企業で会議室の予約ログを分析したところ、全予約の約3割が使用されていない「空予約」だったという例もあります。これは見た目上の稼働率を著しく上げてしまい、本当に使いたい人が予約できないという本末転倒な状況を生み出します。
さらに、こうした空予約が常態化すると、必要以上に多くの会議室を抱える結果になり、固定費の無駄につながることも。
定期的にログを分析することで、こうした隠れた非効率に気づくことができます。
利用実績に基づく費用配分で、コスト意識を全社的に高める
稼働率の可視化は、単なる運用改善にとどまらず、ファシリティの費用配分を適正化する仕組みづくりにもつなげられます。
たとえば、会議室の使用状況を部門別に集計し、それに応じて施設維持費を配分すれば、コストの“見える化”と責任の明確化が実現できます。
「営業部門は会議室使用時間が他部門の2倍」「管理部門は予約率は高いがキャンセル率も高い」などといった部門ごとの使い方が見えてくれば、利用の見直しや最適化が促されます。
これにより、不要な予約の抑制や会議の効率化が進み、全社的なコスト意識の向上にもつながっていきます。
稼働率分析に使えるツールとデータ活用法
ここでは、稼働率分析を“勘”や“印象”から脱却させ、客観的なデータにもとづく判断を可能にするツールや仕組みを紹介します。
会議室予約システムは「稼働率分析ツール」でもある
多くの企業で導入されている会議室予約システムは、稼働率分析にとっても優れた情報源となります。日時・部屋ごとの予約履歴だけでなく、チェックイン機能やセンサー連携によって「実際に使われたかどうか」まで記録することが可能です。
ログを活用することで、空予約の頻度や人気の時間帯・部屋などの傾向を客観的に把握できます。
ログデータから見える使用傾向と改善ポイント
「毎週月曜の朝は稼働率が高い」「午後はどの部屋も空いている」…ログデータを蓄積していくと、こうした時間帯や曜日ごとの傾向が見えてきます。
そこから、たとえば「午後の会議室をチームミーティングに転用」「予約時間を30分単位に細分化」など、運用ルールの見直しにつながります。分析→仮説→改善のサイクルが回る仕組みづくりが重要です。
ツールで稼働率を見える化し、改善提案につなげる5ステップ
ログが取得できる仕組みを導入しても、使いこなせなければ意味がありません。この章では、予約システムやログデータを使って会議室の稼働率を“見える化”するための実践ステップを紹介します。
ステップ1:ログを取得できる予約システムを確認・準備
まずは会議室予約システムの機能を確認します。「予約履歴のエクスポート」や「チェックイン機能」があるかを見ておきましょう。CSVでの出力が可能であれば、ExcelやGoogleスプレッドシートでの分析に活用できます。
ステップ2:稼働状況データを集計し、基本指標を算出
ダウンロードした予約ログを使って、稼働率、空予約率、曜日別の利用頻度などの指標を計算します。関数やピボットテーブルを使って時間帯別に傾向を可視化しておくと、後の分析やレポート作成がスムーズになります。
ステップ3:実使用を記録する仕組みを導入・連携
予約だけでは「実際に使われたか」がわかりません。チェックイン機能やセンサー、ビーコンを活用し、利用の有無を正確に取得できるようにします。
これにより空予約の割合を正確に把握でき、リアルな稼働実態をつかむことができます。
ステップ4:データを可視化して“伝わる資料”にする
収集したデータは、グラフやヒートマップなどにして直感的に見せることが大切です。「どの部屋が使われすぎか」「いつ空いているか」が一目でわかるように可視化することで、社内共有や提案時の説得力が格段に上がります。
ステップ5:レポートを改善提案へと昇華
ただデータを並べるだけでなく、「どんな課題が見えたか」「どう改善すればよいか」という“ストーリー”を加えてレポートをまとめます。「午後の稼働率が低い→別用途に転用」「予約が集中→ルールの見直し」など、アクションに直結する提案に落とし込むことが重要です。
実際の改善事例|稼働率分析がファシリティ最適化に貢献したケース

会議室の稼働率を分析した結果、ファシリティマネジメントの精度が大きく向上した企業は少なくありません。この章では、実際にツール導入と分析を行った企業の改善事例をご紹介します。
会議室の削減・レイアウト変更を後押しした分析結果
あるIT企業では、全会議室のログを半年間収集・分析したところ、6室中2室の稼働率が30%未満だったことが判明しました。
最初は「いつも予約がいっぱい」との印象を持っていたものの、実際は予約だけで利用されていないケースが多数ありました。
この結果を受け、2室をフリーアドレススペースに変更したところ、社員同士のコラボレーションが増え、会議の質と生産性が向上したといいます。稼働率の可視化がなければ、こうしたレイアウト変更の判断は難しかったはずです。
ツール導入により利用満足度が向上した企業の声
別の企業では、センサーと予約システムを連携させた結果、空予約のキャンセル率が大幅に改善。使われない予約が自動キャンセルされる仕組みを導入したことで、実際に使いたい人が空きを見つけやすくなり、「取りにくかった会議室がスムーズに取れるようになった」と社員からの評価も高まりました。
テクノロジーはその活用の仕方によって、日常の不満を解決するパートナーにもなり得るのです。
まとめ
企業が抱える「会議室が足りない」「オフィスが使いづらい」といった悩みの多くは、実は「正しく現状を把握できていないこと」に起因します。予約システムのデータやセンサーのログを活用すれば、見えづらかった非効率が浮かび上がり、改善への一歩を踏み出せます。
あなたの提案が、企業の働き方そのものを変えるかもしれません。

