ハイブリッドワークの最適な管理法|総務が押さえるべきポイントとは?
コラム
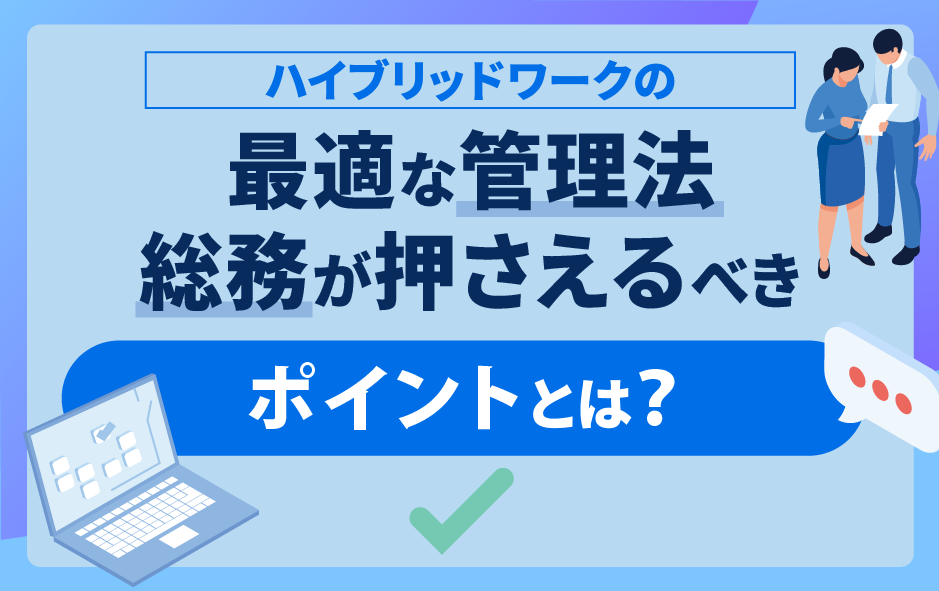
ハイブリッドワークが定着する中、企業の総務担当者やマネージャーは、社員の管理方法に新たな課題を感じているのではないでしょうか。オフィス勤務とリモート勤務を組み合わせた働き方は、柔軟性や生産性の向上といったメリットがある一方で、管理が難しくなるという側面も持ち合わせています。本記事では、ハイブリッドワークの管理に関する具体的な課題とその解決策を、実践的な視点から解説していきます。
ハイブリッドワークにおける管理の課題とは?
ハイブリッドワークの普及により、企業は新たな管理課題に直面しています。業務の進捗管理や勤怠管理、社員間のコミュニケーションの難しさなど、従来の働き方にはなかった課題が浮き彫りになっています。ここでは、ハイブリッドワーク特有の管理の難しさについて詳しく解説します。
業務進捗を可視化しにくい
リモートとオフィス勤務が混在する環境では、チーム全体の進捗を把握しにくくなります。対面での報告やちょっとした雑談が減るため、作業の遅れやボトルネックが発生しても気づきにくいのが現状です。
進捗の可視化を行うには、タスク管理ツールの導入が有効です。たとえば、プロジェクト管理ツールを活用すれば、各メンバーの進捗をリアルタイムで確認でき、適切なサポートを提供できます。また、進捗報告のタイミングを明確にすることで、作業の遅延を防ぐことも可能です。
リモート社員との連携不足
リモートワークでは、オフィス勤務者との間に情報格差が生まれやすく、連携不足が生じることがあります。たとえば、オフィスでの会話で決まったことがリモート勤務者に伝わらないと、認識のズレが発生し、業務の非効率化につながります。
この問題を解決するには、情報共有のルールを明確にし、意識的にオンラインでのコミュニケーション機会を増やすことが重要です。会議の議事録を必ず共有する、チャットツールを活用して意思決定の過程を記録するなどの工夫が求められます。
勤怠管理が複雑化
ハイブリッドワークでは、勤務時間や働く場所が柔軟になり、勤怠管理が難しくなります。リモート勤務の日数や時間を正確に把握できないと、長時間労働の発生や勤務実態の把握不足につながることがあります。
この課題に対応するために、勤怠管理ツールを活用し、リモート勤務時の労働時間を可視化することが大切です。従業員が自身の勤務状況を簡単に報告できるシステムを整えることで、透明性のある管理が可能になります。
セキュリティ対策の強化が必須
リモート環境では、会社のデータを個人デバイスで扱う機会が増えるため、情報漏えいのリスクが高まります。特に、公共のWi-Fiを利用した際にデータが流出する可能性もあるため、企業は厳格なセキュリティポリシーを策定する必要があります。
具体的には、VPN(仮想プライベートネットワーク)の導入や、多要素認証(MFA)の設定を行い、不正アクセスを防ぐことが重要です。さらに、従業員向けにセキュリティ教育を実施し、安全なデバイスの使い方を周知することも有効です。
社員のモチベーション低下
リモートワークが続くと、社員同士の交流が減少し、モチベーションの低下につながることがあります。特に、新入社員や異動したばかりのメンバーにとっては、社内の雰囲気がつかみにくく、孤独感を感じやすい環境になりがちです。
これを防ぐには、オンラインでの雑談スペースを設けたり、定期的なチームイベントを開催することが有効です。また、1on1ミーティングを実施し、個々の社員が抱える悩みや課題をヒアリングすることで、心理的安全性の高い職場をつくることができます。
効果的なハイブリッドワーク管理のためには?

ハイブリッドワークを成功させるには、適切な管理方法を確立することが不可欠です。業務ルールの明確化や出社状況の可視化を行うことで、社員の混乱を防ぎ、スムーズな業務遂行が可能になります。ここでは、実践的な管理のポイントについて解説します。
業務ルールを明確化し、社員の混乱を防ぐ
ハイブリッドワークでは、どの業務をリモートで行い、どの業務に出社が必要なのかを明確にしておかないと、社員が判断に迷うことになります。たとえば、「週○日は必ず出社」「○○の業務はオフィスで実施する」など、企業ごとの業務フローを明確にすることで、業務の円滑な進行が可能になります。
また、連絡手段の統一も重要です。業務の指示はメール、日常的なやりとりはチャットツール、重要な決定はオンライン会議など、用途ごとにツールを使い分けるルールを設定することで、情報の伝達ミスを減らすことができます。
座席管理ツールで社員の出社状況を見える化
オフィスへの出社が任意の場合、「誰がいつ出社しているのか」が分からず、対面での打ち合わせや連携が難しくなることがあります。これを解決するために、座席管理ツールを活用し、出社状況を可視化することが有効です。
たとえば、出社予定を事前に登録できるシステムを導入すれば、誰がオフィスにいるのかが一目で分かり、オフラインでの会議調整がスムーズになります。また、出社率のデータを分析することで、オフィスの最適な運用方法を検討する材料にもなります。
ハイブリッドワーク導入時の注意点
ハイブリッドワークを導入する際には、スムーズな運用を実現するための準備が必要です。特に、働く環境の公平性や評価制度の見直し、継続的な改善を行うことが求められます。ここでは、導入時に気をつけるべきポイントについて詳しく解説します。
自宅・オフィスの環境差による不公平を解消する
リモートワークを選択する社員とオフィス勤務の社員の間で、働く環境の違いが生じることがあります。たとえば、リモートワークでは「通信環境の質」「作業スペースの快適さ」などが個々の状況に依存し、結果として生産性の差が生まれる可能性があります。
この問題を解決するために、企業側で必要なサポートを提供することが重要です。たとえば、以下のような施策が有効です。
- リモートワーク手当の支給:通信費や電気代の一部を会社が負担する
- 業務用デバイスの支給:自宅でも快適に作業できるよう、PCやモニター、ヘッドセットを貸与する
- ワーキングスペースの提供:コワーキングスペースの利用補助や、自社サテライトオフィスの開設を検討する
こうした取り組みによって、働く場所の違いによる不公平感を最小限に抑えることができます。
リモート勤務者の評価が不利にならない仕組みをつくる
ハイブリッドワークでは、オフィス勤務の社員とリモート勤務の社員の評価基準が異なってしまうことがあります。特に、オフィスで直接上司と関わる機会が多い社員のほうが評価されやすい「出社バイアス」が発生しやすい点に注意が必要です。
これを防ぐためには、成果ベースの評価基準を明確にし、業務のプロセスやアウトプットを適切に記録する仕組みを整えることが大切です。たとえば、以下のような方法が効果的です。
- KPIやOKRを設定し、成果を定量的に評価する
- 評価面談では、勤務形態にかかわらず公平な基準でフィードバックを行う
- 自己評価シートや業務ログを活用し、リモート勤務でも成果を可視化する
このような工夫を取り入れることで、リモート勤務者が正当に評価される環境を整えることができます。
運用開始後も継続的に改善し、最適化を図る
ハイブリッドワークの制度は、一度導入すれば終わりではありません。社員の働き方やニーズは常に変化するため、定期的なフィードバックをもとに改善を重ねることが不可欠です。
たとえば、以下のような施策を取り入れることで、より良い制度設計が可能になります。
- 社員アンケートを定期的に実施し、課題を把握する
- ハイブリッドワーク推進チームを設置し、運用の最適化を進める
- 試験的な施策を導入し、小規模での効果を検証する
企業の成長とともに、働き方の最適解も変化します。常に改善を意識しながら、より柔軟で働きやすい環境を整えていきましょう。
ハイブリッドワークでも活発なコミュニケーションを生み出すには

ハイブリッドワークでは、オフィス勤務とリモート勤務が混在するため、社員同士のコミュニケーションが不足しがちです。情報共有の遅れや一体感の低下を防ぐために、オンラインとオフラインを効果的に組み合わせる工夫が求められます。ここでは、コミュニケーションを活性化する具体的な施策について解説します。
会議の目的に応じて最適な形式を選ぶ
ハイブリッドワーク環境では、対面会議とオンライン会議を適切に使い分けることが重要です。会議の目的に応じた形式を選ぶことで、意思決定のスピードや議論の質を向上させることができます。
- ブレインストーミングやアイデア出し → 対面会議を推奨
- 対面での会話は、自然なアイデアの発散や意見のキャッチボールを促しやすい
- ホワイトボードや付箋を活用しながら、直感的に意見を整理できる
- 進捗確認や情報共有 → オンライン会議を活用
- 短時間で端的に情報を共有でき、全員が効率的に参加可能
- 画面共有やチャット機能を活用すれば、リアルタイムで補足情報を伝えやすい
また、オンライン会議では発言者が偏らないよう、チャット機能や投票機能を活用することで、全員が意見を出しやすい環境を整えることも大切です。
定期的な1on1で社員の課題や悩みを見える化
リモートワークでは、社員が個別に抱える課題や悩みに気づきにくくなるため、定期的な1on1ミーティングを実施することが効果的です。特に、直属の上司が社員の状況を把握し、適切なサポートを提供できる環境を整えることが求められます。
- 業務の進捗だけでなく、働き方やキャリアの相談も含める
- 「今後どのようなスキルを伸ばしたいか」「仕事をしていて困っていることはあるか」といった質問を投げかける
- 上司が指導する場ではなく、社員の意見を引き出し、サポートする場として活用する
- リモート勤務者が話しやすい雰囲気を作る
- 形式ばった会話だけでなく、雑談を交えながら進めることで、リラックスした雰囲気を作る
- 画面越しでもアイスブレイクを設けることで、率直な意見を引き出しやすくする
- 会話の内容を記録し、次回以降のミーティングに活かす
- 「前回の1on1で話した内容から、どのような変化があったか」を振り返り、継続的なサポートにつなげる
- 目標や課題をメモに残し、フィードバックの一貫性を確保する
このように、1on1を単なる業務報告の場ではなく、社員の成長や満足度向上の機会とすることで、ハイブリッド環境においても強い組織を作ることができます。
ハイブリッド環境でも維持できる企業文化の作り方
ハイブリッドワークでは、オフィスでの自然な交流が減るため、企業文化の維持が課題となります。企業のビジョンや価値観を社員に浸透させるには、オンライン・オフラインを問わず、積極的に社内コミュニケーションを促進する仕組みが必要です。
- オンライン社内イベントの開催
- 「バーチャルランチ」や「オンラインゲーム大会」など、気軽に交流できる機会を定期的に設ける
- フォーマルなイベントだけでなく、カジュアルな集まりを通じて、社内のつながりを強化する
- 社内SNSやチャットツールでの雑談スペースの設置
- 「仕事以外の雑談OK」のチャンネルを作り、趣味や興味を共有できる場を提供する
- 社員が自発的に交流できる環境を作ることで、オフィス勤務者とリモート勤務者の距離を縮める
- オフィス勤務の日に社内交流の機会を増やす
- 出社日に合わせて「ランダムランチ制度」を導入し、異なる部署のメンバーと交流できる機会を作る
- チーム全体での対面ミーティングを定期的に設定し、業務以外の会話が生まれやすい場を意図的に設ける
こうした施策を取り入れることで、物理的な距離に関係なく、組織としての一体感を維持しやすくなります。
まとめ
ハイブリッドワークを成功させるためには、適切な管理体制を整え、社員が快適に働ける環境を構築することが不可欠です。業務進捗の可視化、評価の公平性、継続的な改善、コミュニケーションの活性化など、多くのポイントを押さえる必要があります。企業ごとに最適な方法を模索しながら、ハイブリッドワークのメリットを最大限に活かせる働き方を実現していきましょう。

