ABW(アクティビティ・ベースド・ワーキング)の働き方の全体像を解説!シーン別の行動スタイルと組織運用のヒント
コラム
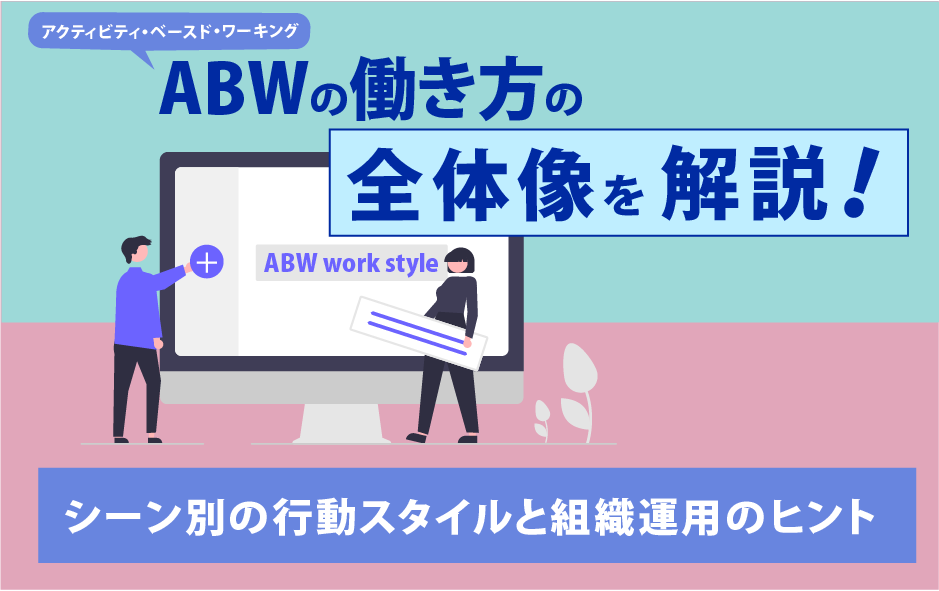 働き方の多様化が進む中で注目を集めているのが「ABW(アクティビティ・ベースド・ワーキング)」というスタイルです。ただのフリーアドレスとは異なり、仕事内容に応じて働く場所やスタイルを自由に選べるこの働き方は、企業にも個人にも大きな変化をもたらします。本記事では、ABWの働き方に焦点を当て、日常の働き方の具体例や組織運用のポイントまで丁寧に解説していきます。
働き方の多様化が進む中で注目を集めているのが「ABW(アクティビティ・ベースド・ワーキング)」というスタイルです。ただのフリーアドレスとは異なり、仕事内容に応じて働く場所やスタイルを自由に選べるこの働き方は、企業にも個人にも大きな変化をもたらします。本記事では、ABWの働き方に焦点を当て、日常の働き方の具体例や組織運用のポイントまで丁寧に解説していきます。
ABW働き方の基本|“働く場所を選ぶ”が前提のスタイル
ABWとは、働く人が業務の内容や目的に応じて「どこで」「どう」働くかを自律的に選択できるスタイルのことです。以下では、この働き方の基本的な特徴を2つの視点から解説します。
ABWは固定席を持たず、仕事内容に応じて働き方を変えるスタイル
ABWの最も大きな特徴は「固定席がない」という点です。従来のように部署ごとの島型レイアウトで座席が決まっているのではなく、その日、その時、その業務に合わせて最適な場所を選ぶことができます。
たとえば、資料作成に集中したい日は静かな個室ブースへ、チームミーティングの日はコラボスペースへ、軽めの業務でリラックスしたい日はカフェエリアへ、といった具合です。座席がフリーであることがゴールではなく、“目的に応じて行動する”ことがABWの真髄です。
こうした働き方により、従業員は業務に最適な環境を自ら選び取れるようになり、結果として生産性や創造性が高まる効果が期待できます。
社内外を自由に移動しながら働く「場所にとらわれない勤務」が前提
ABWは「オフィスの中だけで完結する働き方」ではありません。社外のコワーキングスペースや自宅、あるいはカフェや出張先なども、すべて働く場所の選択肢として含まれます。
たとえば、午前中はオフィスでチーム会議に参加し、午後は自宅で資料作成に集中。翌日はクライアント訪問の前後で、駅近のワークスペースを使ってメールチェックや報告書作成――そんな流動的な働き方がABWの基本です。
このようなスタイルを実現するには、社内ネットワークへのリモートアクセスやノートPCの貸与、クラウドツールの整備など、インフラの充実が欠かせません。同時に、「どこで働くか」ではなく「何を成果として出すか」を評価する視点も重要になってきます。
ABWの働き方を支えるシーン別働き方4パターン
ABWでは「業務の内容に応じて最適な環境を自分で選ぶ」という考え方がベースにあります。では、具体的にどんなシーンでどのような働き方をするのでしょうか。ここでは代表的な4つのシーンに分けて、その働き方を解説します。
集中したいとき:静かなエリアや個室スペースでのソロワーク
資料作成や分析業務、考えをまとめたい場面では、周囲の音や会話が少ない静かな場所が求められます。ABWのオフィスでは、こうしたニーズに応えるために「フォーカスエリア」や「集中ブース」などが用意されていることが一般的です。
周囲を気にせず自分のペースで仕事ができることで、作業効率が上がり、業務の質も向上します。また、業務内容に応じて短時間だけ利用することもでき、オン・オフの切り替えにも効果的です。
チームで協働するとき:プロジェクトスペースやコラボエリアでの対話型作業
一方で、チームでアイデアを出し合ったり、複数人でプロジェクトを進めるときには、周囲との距離が近く、コミュニケーションがとりやすい空間が必要になります。ABWでは「コラボレーションエリア」や「プロジェクトルーム」がこの役割を果たします。
ホワイトボードや大型モニターを設置したスペースで、資料を見ながら意見交換をしたり、立ち話感覚での素早いミーティングが可能になります。目的に応じてスペースを選べることで、会議の質もテンポも上がります。
気分転換やアイデア出し:カフェ風ラウンジやリフレッシュ空間の活用
長時間のデスクワークでは集中力が切れてしまうこともあります。そんなときに有効なのが、あえて“少し緩めの空間”で働くことです。ABWのオフィスでは、カフェ風のラウンジスペースや植物に囲まれたリラックスエリアを用意しているケースもあります。
これらの空間では、あえて堅苦しさを取り払うことで、自由な発想が生まれやすくなります。ノートPC片手にドリンクを飲みながらの作業や、偶発的な会話からアイデアが生まれることも少なくありません。
リモートも活用:自宅・外出先・シェアオフィスを使った分散ワーク
ABWは「オフィス以外でも働ける」ことを前提としたスタイルです。自宅でのリモートワークはもちろん、地方拠点やシェアオフィス、さらには移動中のカフェなども仕事場の選択肢になります。
たとえば、午前中に訪問先の近くのコワーキングスペースでメールを処理し、午後は帰宅して自宅で報告書を作成する、といった柔軟な働き方が可能になります。この自由度の高さが、従業員満足度の向上や離職防止にもつながっています。
ABWにおける従業員の時間とタスクの自己管理術
ABWでは、自由な働き方が可能になる一方で、従業員一人ひとりの「自己管理力」が強く求められます。ここでは、時間管理・業務の選択・ツール活用という3つの観点から、ABWで必要となる自己管理術を解説します。
成果主義・ジョブ型に近い考え方で、勤務時間よりアウトプットを重視
ABWにおける働き方では、「何時間働いたか」よりも「何を成果として出したか」が重視されます。これは、いわゆる“ジョブ型”に近い評価軸ともいえます。結果として、勤務中の行動は上司に逐一見られるわけではなく、自分で責任を持って成果を出す姿勢が求められます。
たとえば、「午後は在宅で集中作業をして、終業時間前に成果物を提出」といった動きも、成果が伴えば問題なし。逆に、長時間オフィスにいてもアウトプットがなければ評価にはつながりません。この考え方に馴染むには時間がかかることもありますが、自律的に働く力が育まれれば、自己成長にもつながります。
タスクごとに自分で働く場所・時間・方法を選択する責任がある
ABWでは、「どこで、いつ、どうやって」仕事を進めるかの選択が常に求められます。これは自由であると同時に、判断力が問われるポイントでもあります。たとえば、資料作成のように集中力が必要な仕事を、あえてカフェスペースで行ってしまうと、思うように進まず非効率になります。
逆に、チーム内のすり合わせが必要なときに個室にこもっていては、コミュニケーションロスが生まれてしまうかもしれません。つまり、「今の業務にはどんな環境が適しているか」を冷静に見極め、自分の行動を選択できることが、ABWの生産性を高める鍵なのです。
自己管理を支援するツールの活用
ABWの働き方を支えるには、デジタルツールの活用も欠かせません。
たとえば、SlackやTeamsなどのチャットツールで常に情報共有を行うことで、どこで働いていてもスムーズな連携が可能になります。また、TrelloやNotionなどのタスク管理ツールを使えば、進捗状況が可視化され、チーム内での役割分担も明確になります。
こうしたツールは、「場所がバラバラでも機能する組織」を支える重要なインフラと言えるでしょう。
ABWを社内で運用するために必要なルールと仕組みづくり
ABWは「自由な働き方」を実現するものですが、完全に無秩序な状態では逆に混乱を招いてしまいます。企業がこの働き方をうまく運用するためには、最低限のルールと、働き方を支える仕組みづくりが重要です。
ABWに適した最低限のルールを明文化
ABWを導入する際には、まず「最低限のルール」を明確にしておくことが必要です。これは、自由を制限するというよりも、共通認識を持つことで社員同士のストレスやトラブルを防ぐためです。
例えば、「集中スペースでは私語を控える」「1時間以上離席する場合は席に荷物を置かない」「オンライン会議は専用ブースで行う」といったルールが挙げられます。こうした基本ルールが明文化されていれば、新しく入った社員もすぐに環境に馴染むことができます。
座席予約システムの導入でフリーアドレスを円滑に運用
ABWのオフィスでは固定席がないため、「今日はどこで仕事をしようか」と毎日考えることになります。しかし、人気のあるエリアが常に埋まっていたり、座る場所を探して移動ばかりになると、生産性が下がってしまいます。
こうした課題を防ぐには、座席予約システムの導入が有効です。事前に座席の空き状況を確認し、使いたいスペースを確保できることで、社員の移動ストレスが軽減されます。特に会議室や集中ブース、コラボスペースなど“用途が限られた場所”は予約制にすることで、全員が公平に利用しやすくなります。
多様な働き方を支える社内カルチャーの醸成
どれだけ制度や設備が整っていても、ABWが根づくかどうかは「組織文化」に大きく左右されます。自由な働き方を認める一方で、「上司が部下の行動を細かく監視したがる」「常に出社している人が評価されやすい」といった旧来の文化が残っていると、ABWの本質は活かされません。
ABWに合ったカルチャーを育てるためには、「成果で評価する」「自由を信頼する」「オープンなコミュニケーションを推奨する」といった価値観を、マネジメント層から社内全体に浸透させていく必要があります。特に、働き方の多様性をポジティブに捉える姿勢を育むことが、長期的な定着に不可欠です。
ABWの働き方を定着させるために企業がすべきこと
ABWは一度制度を整えれば終わりというものではありません。導入後にいかに現場で定着させ、社員が自律的に活用できるようになるかが成功のカギです。このセクションでは、企業が取り組むべき具体的なアクションを紹介します。
導入前後で「どう働くか」を共有するオンボーディング施策
ABW導入時には、「自由に働いていい」とだけ伝えてしまうと、現場は戸惑ってしまいます。そこで重要なのが、導入時に「ABWとは何か」「どう行動すればよいのか」を丁寧に説明するオンボーディングの場を設けることです。
例えば、事前に説明会やワークショップを開催し、ABWの目的・使い方・期待される行動について共通理解を深めておくとスムーズです。導入初期には「ロールモデル社員」を設けて行動を可視化したり、実際の利用風景を社内のコミュニケーションツールで発信するのも効果的です。
部門ごとの最適なスタイルを模索する柔軟な運用体制づくり
ABWの理想的な形は、企業全体で一律に決められるものではありません。営業部門、バックオフィス、クリエイティブチームなど、職種や業務内容によって最適な働き方は異なります。
そのため、ABWはある程度の「個別最適」ができる体制を組んでおくとよいでしょう。たとえば、部門単位で座席の使い方を工夫したり、チームごとにミーティング頻度を調整したりと、現場主導で柔軟に設計していくことが求められます。「全社で共通する基本ルール」+「部門別で最適化する運用」が理想的なバランスです。
フィードバックを重ねて、制度・設備・人の最適バランスを探る
ABWの働き方は、導入して終わりではなく、常にアップデートが必要です。社員からの声を定期的に収集し、「このエリアが足りない」「使いづらいツールがある」「もっと静かな場所が欲しい」といったフィードバックをもとに、制度や環境を見直す仕組みが不可欠です。
アンケートや1on1、オフィスラウンドなどを通じて現場の声を吸い上げ、小さな改善を重ねていくことが、ABWの働き方を定着させる最大のポイントです。また、人事評価や労務管理の観点からも「ABWに合った運用」へと徐々にシフトしていくことが求められます。
まとめ
ABWは、単なる座席のフリー化ではなく、働く人が自律的に「業務に最適な環境」を選び、成果を出すための考え方です。シーンに応じて働く場所を変え、チームと個人のバランスを取りながら働けるこのスタイルは、企業の生産性や柔軟性を高める可能性を持っています。
その一方で、自己管理や運用ルール、社内カルチャーの整備といった「見えない部分」の支援がなければ、うまく機能しない側面もあります。ABWを本当の意味で“活かす”には、制度・設備・人のバランスを見ながら、企業全体で取り組んでいく姿勢が重要といえるでしょう。

