ABW(アクティビティ・ベースド・ワーキング)導入事例と導入に適した企業の特徴|働き方改革のヒントと成功のポイントを解説
コラム
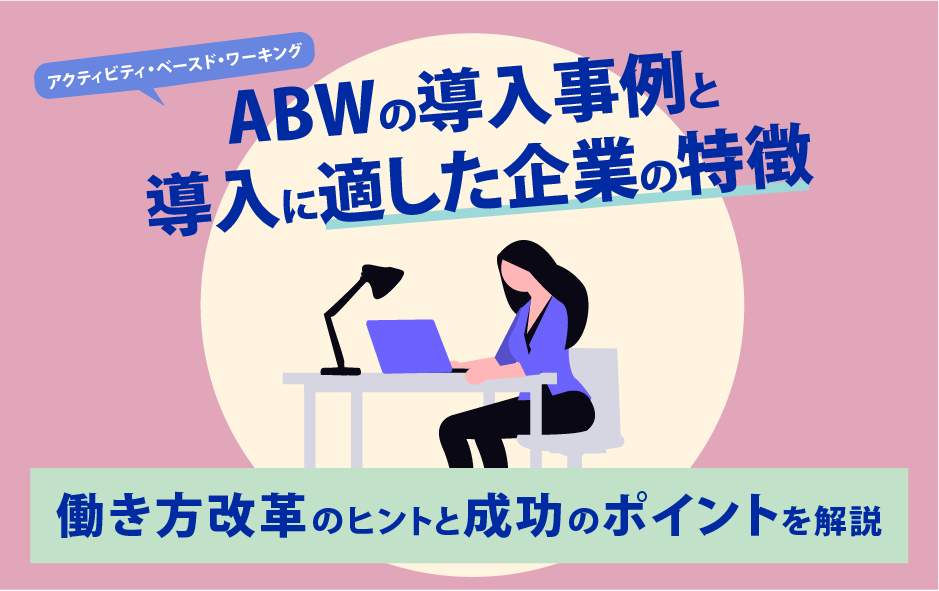 リモートワークや出社のハイブリッド化が進む中で、ABW(Activity Based Working)は、企業に新たな働き方の可能性をもたらしています。しかし「本当に自社に合うのか」「どんな効果が期待できるのか」と悩む方も多いのではないでしょうか。本記事では、ABWを導入した企業の事例をもとに、導入に適した企業の特徴や注意点をわかりやすく解説します。
リモートワークや出社のハイブリッド化が進む中で、ABW(Activity Based Working)は、企業に新たな働き方の可能性をもたらしています。しかし「本当に自社に合うのか」「どんな効果が期待できるのか」と悩む方も多いのではないでしょうか。本記事では、ABWを導入した企業の事例をもとに、導入に適した企業の特徴や注意点をわかりやすく解説します。
ABWの導入事例|企業の成功パターンを学ぶ
ABWの導入は、企業によってまったく異なる目的とプロセスで行われています。ここでは、10の事例をピックアップ。組織の特性に応じた導入の工夫や、導入後に起きた変化に注目し、自社に近いケースからヒントを探してみてください。
多拠点化企業|チーム横断のコラボレーションが活性化
複数の拠点を抱えるある企業では、拠点が増えるほどに部門同士の壁が厚くなり、情報が滞ってしまうなど、「オフィス間の連携不足」が大きな課題でした。そこでABWを導入し、部署や支店にとらわれず、業務内容やプロジェクトごとに座席を選べるようにしたところ、社員同士の交流が一気に広がったのです。離れた拠点同士でも「誰がどこで何をしているか」が見えるようになり、打ち合わせの頻度やスピードも向上。ABWが物理的な距離を縮める橋渡しになりました。
クリエイティブ業種|集中と発想を支えるゾーニング設計
広告やデザイン、映像制作などの業種では、“ひらめき”が成果を左右します。ある企業は、ABWを導入する際、空間を「考える・話す・つくる」といった活動に合わせて明確にゾーン分けしました。たとえば、静けさを保つ「集中エリア」では個人作業が進みやすく、一方で「コラボエリア」ではメンバーが壁に付箋を貼りながらブレストを展開。空間の違いが思考を切り替えるスイッチとなり、社員の間でも場所によって脳の使い方を変える感覚が根づいていきました。
IT企業|リモートワークと出社のハイブリッド対応
リモートワークが浸透したIT企業では、「出社したくなる理由づくり」が課題でしたが、ABWを活かして、予約制のワークスペースや、1人用のWeb会議ブース、集中ルームを整備。業務内容に応じて場所を選べる自由度が、出社の心理的ハードルを下げただけでなく、目的意識のある出社へと変化させました。「今日は集中したい」「対面で話したい」そんな理由が明確になることで、出社自体が価値ある体験に変わったのです。
若手比率の高い企業|自律的に働く文化の定着に成功
社員の7割が20〜30代という企業では、ABW導入が「働き方を自分でデザインする」という文化の定着に一役買いました。たとえば、午前中は静かな席で企画を練り、午後はチームの集まるエリアで進捗共有、夕方はカフェエリアでリラックスしながら資料を整理——そんな1日の流れを社員自身が組み立てられる環境ができたのです。管理職からは「若手の判断力と責任感が目に見えて伸びてきた」との声もあり、ABWが人材育成にも貢献していることが伺えました。
中小企業|省スペースでABWのメリットを最大化
限られた空間を有効活用したい中小企業にとっても、ABWは非常に有効です。ある社員数40名ほどの企業では、固定席をなくし、3つの用途別スペース(静かに作業できる集中ブース、小人数で使える打ち合わせコーナー、自由に過ごせるカフェスペース)を設けました。結果、オフィスの滞在率は以前と同じでも、使われ方のバリエーションが圧倒的に増え、社員同士の関係性や業務のスピードに変化が表れました。「空間を増やさず、使い方を変える」という発想が、ABWによって実現できたのです。
製造業の本社部門|管理部門の業務効率が大幅改善
製造現場を支える本社の間接部門は、業務の属人化や縦割り体制が根深く残っているケースが多く見られます。ある製造業の本社では、総務・経理・人事がそれぞれ固定席で仕事をしていたため、隣のチームの業務内容を知らないという状況がありました。そこでABWを導入し、部門横断で座席を選べるようにしたところ、たとえば「人事と経理で自然と会話が生まれ、採用コストの見直しにつながった」といった効果が見られるようになったのです。業務の流れを“線”でとらえ直すことが、結果として生産性の向上をもたらしました。
金融機関|保守的文化でも柔軟な働き方を実現
コンプライアンスや対面対応が求められる金融機関では、「フリーアドレスなんて無理」と思われがちです。しかし、ある金融系の企業では、まず一部の後方事務部門からABWを試験導入。「どの席に座っても、すぐ業務に取りかかれる」ようにPC・文具類を徹底的に標準化し、ITサポートを手厚くしました。また、毎朝の座席くじやランチ交流など、文化醸成の取り組みも加えることで、形式だけでなく「動きたくなる雰囲気」も整備。少しずつ「席に縛られない働き方」が受け入れられていきました。
グローバル企業|ABW+多言語・多文化対応オフィスへ
複数国に拠点を持つグローバル企業では、ABWの導入が「多様性の受け皿」としても機能しています。ある企業では、英語をはじめとする多言語表記の案内や、食文化・宗教を尊重した休憩スペースの工夫など、空間設計にもDEI(多様性・公平性・包括性)の視点を反映。ABWによって「どこで働くか」だけでなく、「誰とどう関わるか」が流動的になり、国籍や部署の壁を超えたチームづくりが加速しました。
営業職中心の企業|出社率のばらつきに対応した最適設計
外出の多い営業職が中心の企業では、日中のオフィスが空っぽになってしまう…という課題がつきものでした。ある企業では、ABW導入にあたって社員の「出社傾向」を徹底的にデータ化。たとえば「水曜午後はほとんど外出」「月曜午前は社内に人が多い」といった傾向に合わせて、席数やゾーンの使い方を柔軟に調整しました。また、短時間の立ち寄りに使えるスタンドデスクや、一時的な荷物ロッカーなども設置し、“滞在時間が短い人にとっても快適な空間”づくりを実現しています。
社内改革推進中の企業|ABWが変革のシンボルとして機能
変化を恐れず、新しい働き方に挑戦したい企業にとって、ABWは「目に見える改革の第一歩」として強いメッセージを持ちます。ある企業では、社内改革プロジェクトの一環としてABWを導入。単にオフィスを刷新したのではなく、空間に込めた意図を社内に共有し、「この働き方は、これからの私たちの姿勢です」と明示することで、若手社員の提案が増えたり、マネージャー層のマインドセットが変化するなど、空間を通じて“空気”が変わる手応えがあったようです。ABWは単なるオフィスレイアウトの変更ではなく、カルチャー変革の触媒にもなり得るといえます。
ABWに適した企業とは?導入にフィットしやすい組織の特徴
ABWはすべての企業に万能なアプローチではありません。自社の業務スタイルや文化との相性を見極めることが、導入の第一歩です。このセクションでは、ABWと親和性の高い組織の特徴を5つ紹介します。該当する項目が多いほど、ABWによって得られる効果は高まる可能性があります。
多様な業務スタイルが混在している企業
ひとつのオフィスに、集中して作業を進めたい人と、頻繁に打ち合わせを行う人が混在している場合、ABWの考え方は非常に有効です。業務内容に応じて働く場所を選べることで、社員それぞれが最もパフォーマンスを発揮できる環境を整えられます。例えば、営業資料の作成は静かなエリアで、午後のチームミーティングはオープンスペースで——といった具合に、活動ごとに最適な空間を活用することが、自然な働き方として定着していきます。
部署間・チーム間の連携を強化したい企業
部門間の壁が厚く、情報共有や連携がうまくいっていないと感じる企業にも、ABWはフィットします。席が固定されていると、どうしても同じ人としか話さなくなり、コミュニケーションの幅が狭まりがちです。ABWでは、座席の流動性によって、異なるチームや職種との偶発的な接点が増えます。実際に「隣の席になったのをきっかけに、プロジェクトがスムーズに進んだ」というような声も多く、組織内のサイロ化を緩やかに解消する効果が期待できます。
出社・在宅のハイブリッド勤務が定着している企業
出社とリモートワークを併用する働き方が定着している企業では、固定席を維持する必要性が薄れてきています。日によって出社人数にバラつきがある場合、ABWによって柔軟にスペースを最適化することで、空間の無駄を減らし、快適な職場環境を維持することができます。また、座席を固定しないことで、「今日は誰とどこで働くか」を日々リフレッシュできる点も、社員のリズムづくりに寄与するでしょう。
若手・自律型人材の割合が多い企業
若手や中堅の社員が多く、自ら考え行動するタイプの人材が多い企業では、ABWの「自分で働く環境を選ぶ」というスタイルが自然に受け入れられやすい傾向があります。自由と責任を両立させる文化がある企業では、ABWによって働き方の選択肢が広がることで、社員のモチベーションや創造性をより引き出すことができます。また、働く場所を選ぶプロセスそのものが、自分の業務内容を俯瞰するきっかけとなり、自然と自律的な行動につながるといえます。
組織変革や働き方改革に積極的な企業
「組織を変えたい」「働き方を見直したい」という意志が明確な企業にとって、ABWは象徴的な一歩になります。単に座席の自由化を図るのではなく、「なぜ変えるのか」「この変化にどんな意味があるのか」といったメッセージを丁寧に伝えることで、空間が企業文化を表現する装置として機能します。社員にとっても、「働く場所が変わる=働き方そのものを見直すきっかけ」となり、ABWが組織変革の足がかりとなるケースも少なくありません。
ABW導入でよくある疑問と解決策
ABWには多くのメリットがある一方で、導入前後にはさまざまな疑問や不安がつきものです。このセクションでは、導入を検討する企業の現場からよく寄せられる3つの声を取り上げ、それに対する具体的な考え方や解決のヒントをお伝えします。
ABW導入でよくある失敗は?
ABW導入の失敗でよく見られるのが、「目的を曖昧にしたまま制度だけを整える」ことです。たとえば「ABW=先進的」というイメージだけで突き進んだ結果、誰がどこにいるのかわからず、結局元の席に戻る…というケースも珍しくありません。
このような失敗を防ぐには、「なぜABWを導入するのか」「何を解決したいのか」といった目的意識を社内で共有することが最も重要です。そのうえで、トライアル導入や段階的なルールづくりを行い、現場のリアルな声を拾いながら調整していくことで、導入の成功率は大きく高まります。
社員のモチベーションを維持する方法は?
「自由な働き方」と聞くとポジティブな印象を持つ方が多い一方で、すべての社員がそれを歓迎するとは限りません。特に、明確な評価軸がないまま自由度だけが高くなると、「何を基準に評価されるのか分からず不安」という声が上がることがあります。
これに対しては、仕事の進め方や成果の出し方について、チームごとに共通認識を持つ仕組みが必要です。定期的な1on1や、目標設定の見える化などを通じて、社員が安心して働ける土台を整えることが、ABWの「自由」と「責任」のバランスを保つポイントになります。
ABW導入のために必要なテクノロジーは?
ABWの柔軟性を現実的に支えるのは、テクノロジーの力です。たとえば、座席予約システムや在席管理ツールがあれば、「どこに誰がいるか」が可視化され、無駄な混乱を防げます。また、オンライン会議に対応した個室ブースや、音声に配慮したパーテーションのあるゾーンは、会話のストレスを減らします。
さらに、ファイル共有やチャットツールなどのクラウドサービスも不可欠です。これらが整っていないと、自由な場所で働ける環境が整っても、実際の業務が滞ってしまう恐れがあります。ABWは空間の工夫だけでなく、それを支える“見えないインフラ”の準備も同時に進めることが成功への鍵です。
まとめ
ABWは、オフィスの“座り方”を変えるだけでなく、組織の“あり方”そのものに変化を促すアプローチです。空間設計や制度だけでなく、自社の課題や文化とどう向き合うかが成功の鍵となります。まずは小さなトライアルから始め、現場の声を取り入れながら運用をアップデートしていくことが大切です。社員が「どう働くか」を自ら選び、行動に移せる仕組みづくりこそ、ABWを“形だけ”で終わらせないための第一歩です。

