ハイブリッドワーク時代の出社率最適化戦略とは? “意味ある出社”を叶えるオフィス設計のヒント
コラム
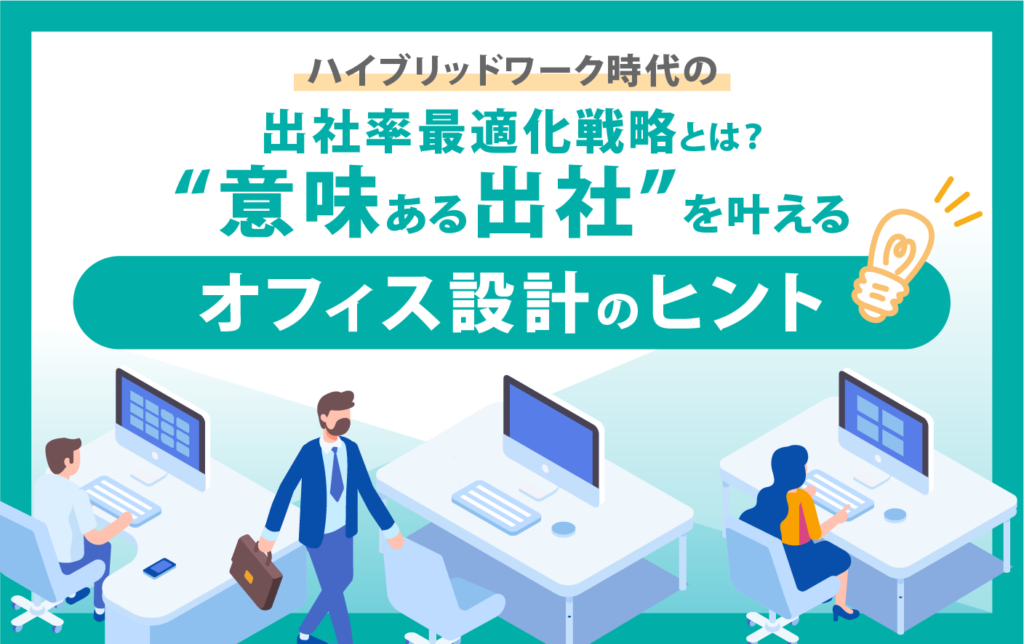
ハイブリッドワークが定着する一方で、「出社しても人がまばら…」「会議室がいつも不足…」「最適な出社ルールが分からない」といったお悩みはありませんか?
この記事では、ハイブリッドワークにおける出社率の考え方から、データに基づいた最適化のアプローチまで、これからのオフィス戦略を考える上で重要なポイントを解説します。
なぜ今、ハイブリッドワークの「出社率最適化」が重要なのか?
ハイブリッドワークが多くの企業で導入される一方、その運用における課題も顕在化しています。
本章では、ハイブリッドワークの現状と企業が直面する新たな課題を整理し、「なんとなく出社」から脱却し「意図ある出社」へ転換する必要性を解説します。
ハイブリッドワークは定着したが…企業が直面する「新たな壁」とは?
新型コロナウイルス感染症の拡大を機に急速に普及したハイブリッドワークは、多くの企業にとって標準的な働き方の一つとなりつつあります。ザイマックス不動産総合研究所の「大都市圏オフィス需要調査2024秋」によれば、企業のハイブリッドワーク利用率(実態)は約74.2%と、出社とテレワークを併用する形態が広く浸透している状況です(※1)。
しかし、その一方で、コミュニケーションの質の低下、チームの一体感の希薄化、情報格差による不公平感、若手社員の育成不安、従業員の孤独感やメンタルヘルスへの影響といった、多岐にわたる新たな課題も浮き彫りになっています。これらの「新たな壁」を乗り越えることが、今後の企業成長の鍵を握るのです。
「なんとなく出社」から「意図ある出社」への転換
ハイブリッドワークの導入初期には、週に数日といった形式的なルールのみで運用されるケースも少なくありませんでした。
しかし、これからは「なぜ出社するのか」「オフィスで何をするのか」という目的を明確にする「意図ある出社」への転換が求められます。オフィスを単なる執務スペースとして捉えるのではなく、従業員同士のコラボレーションを促進し、新たなアイデアを生み出す場、あるいは企業文化を醸成するハブとしての価値を再定義することが重要。
従業員一人ひとりが、出社の意義を理解し納得することで、働きがいにも繋がるでしょう。
出社率の見直しが企業にもたらすメリットとは
出社率を戦略的に見直すことは、企業に多岐にわたるメリットをもたらします。
例えば、業務内容やプロジェクトの特性に合わせて最適な出社頻度を設定することで、従業員の生産性向上や創造性の発揮が期待できます。また、オフィススペースの利用効率を高めることで、賃料や光熱費といったファシリティコストの最適化にも貢献。さらに、従業員のエンゲージメント向上や、企業文化の維持・強化といった組織運営における重要な要素にも影響してきます。
では、具体的に「出社率」とは何を指し、どのように考えれば良いのでしょうか。次の章で詳しく見ていきましょう。
ハイブリッドワークにおける「出社率」を理解する
ハイブリッドワークの文脈で語られる「出社率」とは、具体的に何を指し、どのように捉えるべきなのでしょうか。
この章では、出社率の基本的な定義と指標としての考え方、そして出社率に影響を与える部門や業務、個人の特性といった多様な要因について解説します。
「出社率」の正しい意味は?最適な指標設定の考え方
一般的に「出社率」とは、従業員がオフィスに出社する頻度や割合を示す指標です。単純に「全従業員の総労働日数に対する総出社日数の割合」で算出されることもありますが、部門ごと、あるいは特定の業務に従事する従業員ごとなど、より細分化して捉えることが肝要となります。出社率を単なる数値目標として設定するのではなく、企業の戦略や業務特性、従業員の働きやすさなどを総合的に勘案し、自社にとっての最適な状態を測るためのKPI(重要業績評価指標)の一つとして位置づけることが、的確な現状把握への第一歩です。
出社率に影響を与える多様な要因(部門・業務・個人)
最適な出社率は、企業全体で一律に決められるものではありません。
例えば、研究開発部門やクリエイティブ部門のように、対面でのディスカッションや偶発的なアイデア交換が重視される業務では、比較的高い出社率が効果的な場合があります。
一方で、定型的な事務作業や個人の集中力を要する業務では、リモートワークの比率を高める方が生産性向上に繋がることも。また、従業員個々の家庭環境や通勤時間、価値観といった個人的な要因も、出社に対する意欲やパフォーマンスに影響を与えるため、柔軟な対応が求められます。
「出社したくなる環境」が従業員のモチベーション向上に
出社は、企業文化の醸成や従業員エンゲージメントの維持・向上において、依然として重要な役割を担っています。オフィスでの雑談や共同作業、上司や同僚との直接的なコミュニケーションは、企業理念の浸透や組織への帰属意識を高める効果が期待できます。
しかし、出社を強制するだけでは、かえって従業員のモチベーションを低下させる可能性も。出社の目的を明確にし、オフィスでしか得られない体験や価値を提供することで、従業員が自律的に「出社したい」と思える環境づくりが、エンゲージメント向上に繋がるのです。
出社率最適化に向けた具体的な検討ステップ

ハイブリッドワークにおける出社率の最適化は、一朝一夕に達成できるものではありません。
この章では、出社率最適化に向けた具体的な3つの検討ステップ、「現状把握」「目的設定」「方針策定」について、それぞれ何をすべきかを詳しく解説します。
【ステップ1】現状把握
データで見る出社状況とオフィス利用実態
出社率最適化の第一歩は、現状を客観的に把握することから始まります。
まずは、部門別・個人別の出社日数や頻度、曜日ごとの出社人数の偏りといった基本的なデータを収集・分析しましょう。それに加え、オフィスのどのエリアがどの程度利用されているのか、会議室の稼働状況、特定の時間帯における混雑度など、オフィススペースの利用実態も詳細に把握することが重要です。
これらの定量的なデータが、感覚論ではない、事実に基づいた課題発見と施策立案の土台となります。
【ステップ2】目的設定
ハイブリッドワークで何を実現したいのかを明確に
次に、自社がハイブリッドワークを通じて何を実現したいのか、その目的を明確に設定します。
例えば、「部門間のコラボレーションを活性化し、新たなイノベーションを生み出したい」「従業員のワークライフバランスを向上させ、エンゲージメントを高めたい」「オフィススペースの効率的な活用により、コストを最適化したい」など、企業によって目的は様々です。この目的が曖昧なままでは、出社率に関する施策も場当たり的なものになりかねません。具体的かつ測定可能な目標設定が、戦略を方向づけるために重要になってきます。
【ステップ3】方針策定
組織の最適な出社ルールやオフィス戦略をデザインする
現状把握と目的設定が完了したら、いよいよ具体的な方針策定です。全部門一律のルールではなく、業務特性やプロジェクトの状況に応じて柔軟に出社曜日を調整できるようなガイドラインを設けることが有効でしょう。
また、オフィスに出社する「意味」を従業員が感じられるよう、対面でのコミュニケーションを重視したチーム活動日を設定したり、特定の業務に集中できるブースを設けたりするなど、オフィスの機能やレイアウトを見直すことも重要。これらの施策は、従業員の意見も取り入れながら、継続的に改善していく姿勢が求められます。
海外の潮流からみる、最適化を成功に導くヒント

自社でのルール設計と並行して、より広い視野を持つことも最適化のヒントになります。
ここでは、海外の考え方を知ることで、これからの働き方を考える上での新たな引き出しとなるはずです。
“集まる意味”を設計する、海外企業のハイブリッド戦略
海外の先進企業では、従業員の裁量に完全に任せるのではなく、企業が意図的に対面の機会を設計する「構造化型ハイブリッドワークモデル」という考え方が主流になりつつあります。McKinseyのレポートによれば、このような意図を持ったアプローチが従業員の満足度や組織文化の向上に繋がるとされています(※2)。
「イノベーションの日」「チームビルディング週間」など、特定の目的に合わせて全社やチームで集まる機会を計画的に設けること。それは、偶発性に頼らずにコラボレーションを生み出す、戦略的な仕組みづくりなのです。
“通勤する価値”のあるオフィスとは?これからの投資の考え方
従業員に出社を促すためには、「通勤してでも行きたい」と思える価値をオフィスが提供する必要があります。
不動産サービス大手のJLLは、未来のオフィスは単なる執務スペースではなく、人々を惹きつける「目的地」としての役割を担う必要があると提唱しています(※3)。最新のテクノロジーを備えた会議室、リラックスして雑談できるカフェスペース、集中と協業を両立させる空間設計など、オフィスへの投資は「出社の目的」を達成するための戦略的な投資と捉え直す視点が求められます。
まとめ
ハイブリッドワークにおける出社率の最適化、そして「これからのオフィス」のあり方を考える上で、万能な答えは存在しません。重要なのは、自社の事業特性、企業文化、そして何よりも従業員の多様なニーズを深く理解し、データに基づいて戦略を練り、継続的に改善していく姿勢です。試行錯誤を繰り返しながら、自社にとっての「最適解」を追求し続けることが、これからの時代を勝ち抜くための、そして真に価値ある働き方を実現するための鍵となるでしょう。
出典
※1/ザイマックス不動産総合研究所:「大都市圏オフィス需要調査2024秋」でみたオフィス利用と今後の意向 (2025年1月22日)
https://soken.xymax.co.jp/2025/01/22/2501-office_demand_survey_2024a/
※2/McKinsey & Company:Hybrid can be healthy for your organization—when done right (2024年2月14日)
https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/the-organization-blog/hybrid-can-be-healthy-for-your-organization-when-done-right
※3/JLL:The future of office design
https://www.jll.com/en-us/insights/designing-workplaces-to-drive-success

