勘や経験に頼らないオフィス改革へ。データ分析で創出する「出社したくなる仕掛け」とは
コラム
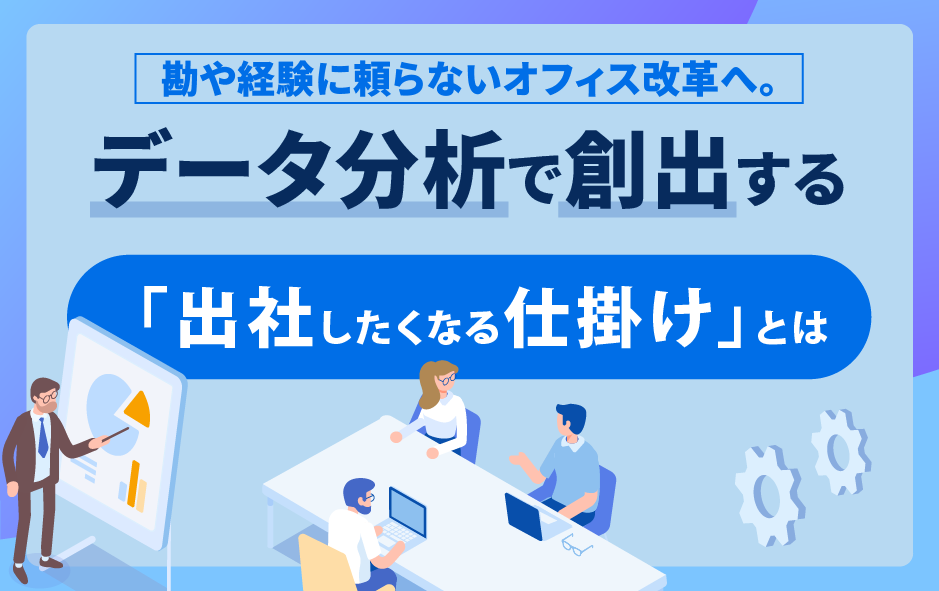
ハイブリッドワークが浸透する中、「オフィスの出社率が上がらない」「従業員のエンゲージメントが低下している」といった課題に対し、感覚的な改善策に限界を感じてはいないでしょうか。
この記事では、勘や経験に頼るのではなく、客観的なデータに基づいて「出社したくなるオフィス」を創り出すための視点とアプローチを解説します。データ活用の基本から、国内外の先進事例、成功のための注意点まで、オフィス戦略を次の一歩へ進めるための思考のフレームワークを提供します。
なぜ今、オフィスに「データ分析」が必要なのか?
ハイブリッドワークが定着したことで、オフィスの役割そのものが問い直されています。
ここでは、なぜ今、データに基づいた客観的なアプローチが不可欠なのか、その背景にある3つの変化を解説します。出社の価値の変化、投資対効果への説明責任、そして人的資本経営という新たな経営の潮流です。
ハイブリッドワークが変えた「出社の価値」とは
リモートワークという選択肢が当たり前になった今、従業員はもはや無条件に出社を選ぶわけではありません。
自宅やカフェでは得られない価値、すなわち「そこでしかできない体験」を求めて、オフィスへと足を運ぶのです。その体験とは、チームメンバーとの偶発的な会話から生まれる新たなアイデアであったり、大型モニターを囲んで行う集中的なディスカッションであったりします。
かつての「働く場所」という画一的な役割から、今は「価値ある体験を得る場所」へと、オフィスの本質的な価値が大きく変化した。この変化への的確な対応こそが、すべてのオフィス戦略の出発点となります。
オフィス施策の効果測定には“データ”が不可欠|ROIをどう示すのか?
「コミュニケーション活性化のためにカフェスペースを新設したが、利用者が一部の従業員に限られている」「Web会議用のブースを増設したが、予約が集中する時間帯と全く使われない時間帯の差が激しい」。
こうした状況は多くの企業で見られます。勘や経験だけに頼った改善は、意図した効果が得られないばかりか、その原因すら特定できません。経営層からは常に投資対効果(ROI)が問われる今、データという客観的な根拠がなければ、「なぜこの施策が必要で、どのような効果が期待できるのか」を合理的に説明することは困難です。
施策の成否を判断し、継続的な改善につなげるためにも、データドリブンなアプローチは不可欠と言えるでしょう。
目的はコスト削減だけではない。「働きがい」を高める人的資本経営の視点
データ活用は、単なるコスト削減や効率化のためだけのものではありません。その先にあるのは、従業員の「働きがい」、すなわちエンゲージメントの向上です。株式会社矢野経済研究所の調査によれば、国内の従業員エンゲージメント診断・サーベイ市場は2023年度に前年度比135.8%となる91億円に達しており、多くの企業がその重要性を認識しています(※1)。データに基づき働きがいを可視化し、改善へとつなげるアプローチは、優秀な人材の獲得と定着に直結する、まさに「人的資本経営」の実践そのもの。オフィス環境が従業員のエンゲージメントにどう影響するかをデータで解明し、改善していくことは、今や重要な経営課題なのです。
データドリブンなオフィス改革のための基本的な考え方

「データを活用する」と言っても、何から始めればよいのでしょうか。
この章では、オフィス改革の基盤となるデータの種類や、分析の基本的な考え方について、順を追って解説します。収集できるデータの種類を理解し、本当に着目すべき指標を見定め、継続的な改善サイクルを回すためのフレームワークを知ることが、成功への第一歩です。
まず何から?オフィスで収集・分析できるデータの種類
データ活用は、既存のシステムからでも始められます。
例えば、会議室予約システムからは「予約時間と実利用時間の差(空予約の実態)」、社員証のログからは「曜日や部署ごとの出社傾向」が把握可能です。さらに一歩進めてIoTセンサーを導入すれば、オフィスの利用実態をより高精度に捉えることができます。人感センサーによって各エリアの稼働率を可視化でき、環境センサーからはCO₂濃度(集中力に影響する換気状況)や騒音レベル(快適性や会話のしやすさ)といった情報も取得可能です。
これらの多様なデータを組み合わせ、多角的に分析することで、これまで見過ごされてきたオフィスの利用実態を客観的に、そして正確に把握するための強固な土台が築かれるのです。
「出社率」の数字だけでは見えない、本当に着目すべき3つの指標
「出社率が30%から40%に上がった」という事実だけでは、オフィスの価値が高まったとは断言できません。
重要なのは、その「質」の内訳を解像度高く見ることです。本当に着目すべきは、例えば「スペース効率性」「コミュニケーション活性度」「従業員エクスペリエンス」といった指標です。特定のエリアに利用が偏っていないか(スペース効率性)、部署を超えた交流が生まれているか(コミュニケーション活性度)、従業員は出社目的に合った活動ができたか(従業員エクスペリエンス)。
こうした具体的な指標に落とし込んで分析することで、初めて本当に意味のある改善のヒントが見えてきます。
継続的な改善を促す、データ活用の基本フレームワーク(PDCA)
データに基づいたオフィス改革は、一度きりのイベントで終わらせてはいけません。
重要なのは、継続的に改善を続ける仕組み、すなわちPDCAサイクルを回し続けることです。
まずは「Plan(現状データから課題を特定し、改善の仮説を立てる)」、そして「Do(仮説に基づいた改善策を実行する)」、次に「Check(再度データを取得し、施策の効果を客観的に検証する)」、最後に「Action(検証結果に基づき、次の改善策へとつなげる、あるいは施策を定着させる)」。
この地道なサイクルを回し続けることこそが、オフィスを真に価値ある場所へと進化させる原動力と言えるでしょう。
データ分析から見つける「出社したくなる仕掛け」の作り方

データは、具体的なアクションに繋がってこそ価値を発揮します。
ここでは、多くの企業が抱えるであろう典型的な課題別に、データをどのように活用して「出社したくなる仕掛け」を創出するのか、国内外の先進事例を交えながら具体的に解説します。課題の裏に隠されたインサイトをデータから読み解き、次の一手へとつなげます。
【課題:コミュニケーション不足】偶発的な出会いを促すエリア設計のヒント
「出社しても結局オンライン会議ばかりで、雑談が生まれない」。これはよく聞かれる悩みの一つです。この課題に対し、人流データを分析して「従業員がどの動線を通り、どこに滞留しているか」を把握することで、意図的に人が交わる「マグネットスペース」を効果的な場所に設置できます。
例えば、利用頻度の高い動線が交わる場所に、少し広めのコーヒースペースや自由に使えるホワイトボードを設置する。データという客観的根拠に基づいて人の流れを設計することで、これまで生まれなかった偶発的なコミュニケーションが誘発され、新たなアイデアの創出につながる可能性が高まります。
【課題:集中環境の不足】生産性を高める「静」と「動」のゾーニング手法
「集中したいのに周りが騒がしい」という悩みは深刻です。
Activity Based Working(ABW)の考え方では、業務内容に応じて働く場所を使い分けることが推奨されます。これをデータで裏付け、より効果的に実現するのがデータドリブンなゾーニングです。エリアごとの滞在時間や騒音レベルをデータで可視化し、「ハイフォーカスゾーン(私語厳禁の集中エリア)」「コラボレーションゾーン(活発な議論を推奨するエリア)」「リフレッシュゾーン」といった形で明確に空間を定義します。
データという客観的根拠に基づいてゾーニングを行うことで、誰もが納得感を持ち、従業員が業務内容に合わせて最適な場所を自律的に選択できる文化が醸成され、オフィス全体の生産性が向上します。
【海外事例に学ぶ】従業員間の「つながり」を可視化するMicrosoft社の挑戦
海外ではさらに進んだデータ活用の事例も見られます。Microsoft社は、自社の分析ツールを用いて匿名化された従業員の行動データを分析し、組織内の「つながりの強さ」を可視化しています(※2)。
分析の結果、ハイブリッドワーク移行後に部門を超えた弱い「つながり」が減少し、イノベーションの機会損失につながる可能性があることを突き止めました。これは、データが単なる施設利用率の最適化に留まらず、組織の創造性を維持・向上させるための戦略的なツールになり得ることを示す好例です。オフィスの役割を「イノベーションを生む場」と再定義する上で、重要な示唆を与えてくれます。
曜日・チーム・時間帯で分析し、利用者の「隠れたニーズ」を掘り起こす
オフィス全体の平均データだけを見ていては、重要なサインを見逃すかもしれません。
「なぜ水曜日の午後に営業部の出社率が高いのか?」「開発チームはどのタイプの座席を好んで利用しているのか」。このように、曜日やチーム、時間帯といったミクロな視点でデータを深掘りすることで、これまで気づかなかった従業員の「隠れたニーズ」が浮かび上がります。
「報告書作成のために集中できる場所を求めている」「大型モニターが使える席で共同作業をしたい」といった具体的なニーズです。そのニーズに応えるきめ細やかな改善こそが、従業員の満足度とエンゲージメントを高める直接的な鍵となるのです。
オフィスデータの活用を成功させるために知っておきたい2つのポイント

データ活用は強力なツールですが、導入や運用には注意すべき点もあります。
最後に、データドリブンなオフィス改革を形骸化させず、着実に成功へ導くための重要なポイントを2つお伝えします。ツール導入の目的を見失わないこと、そして何よりも従業員からの信頼を得ることです。
ツール導入がゴールではない。陥りがちな落とし穴と対策
高機能な分析ツールを導入しただけで満足してしまうのは、最も陥りやすい落とし穴です。
重要なのは、ツールを使って何を知り、どう改善につなげるかという「目的」を明確に持ち続けることです。
「なぜデータを集めるのか?」「そのデータを見て何を判断したいのか?」という問いが曖昧なままでは、集めたデータをどう解釈すればよいか分からず、結局使われなくなってしまいます。まずはスモールスタートでも構いません。
「会議室の空予約を30%削減する」「特定のエリアの混雑を緩和する」といった具体的で達成可能な目標を定め、仮説検証を繰り返しながら活用範囲を広げていくことが成功への近道です。
最も重要なのは信頼。従業員のプライバシーへの配慮と丁寧な合意形成
従業員の行動データを扱う上で、プライバシーへの配慮は何よりも優先されるべき絶対条件です。
まず、「誰が、いつ、どこにいたか」といった個人が特定できるデータは原則として取得・利用せず、あくまで組織全体の傾向を把握するための統計データとして扱うことを徹底します。その上で、「なぜデータを収集するのか」「どの範囲のデータを」「どのように活用するのか」を明確に定めた社内ガイドラインを策定し、全従業員に公開することが不可欠です。説明会などを通じて丁寧に目的を伝え、質疑応答の機会を設けるなど、透明性を確保し、従業員からの信頼を得るプロセスを省略してはなりません。この誠実な対話こそが、改革を成功に導く基盤となります。
まとめ
ハイブリッドワークという大きな変化の波の中で、私たちは今、オフィスの存在意義を根底から問い直す局面に立っています。「出社したくなる日」とは、企業が一方的に与えるものではなく、従業員一人ひとりの多様な働き方のニーズに応えることで、結果として生まれるもの。データを真摯に読み解き、改善を繰り返すプロセスは、いわばオフィスという空間を通じて従業員と対話し、共に価値を創り上げていく営みと言えるでしょう。
出典
※1/株式会社矢野経済研究所「従業員エンゲージメント市場に関する調査を実施(2024年)」:https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3587
※2/Microsoft “The effects of remote work on collaboration among information workers”:https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/the-effects-of-remote-work-on-collaboration-among-information-workers/

