「タスクマスキング」に要注意!生産性を下げる“見せかけの仕事”を防ぐ、集中できるオフィス設計のコツ
コラム
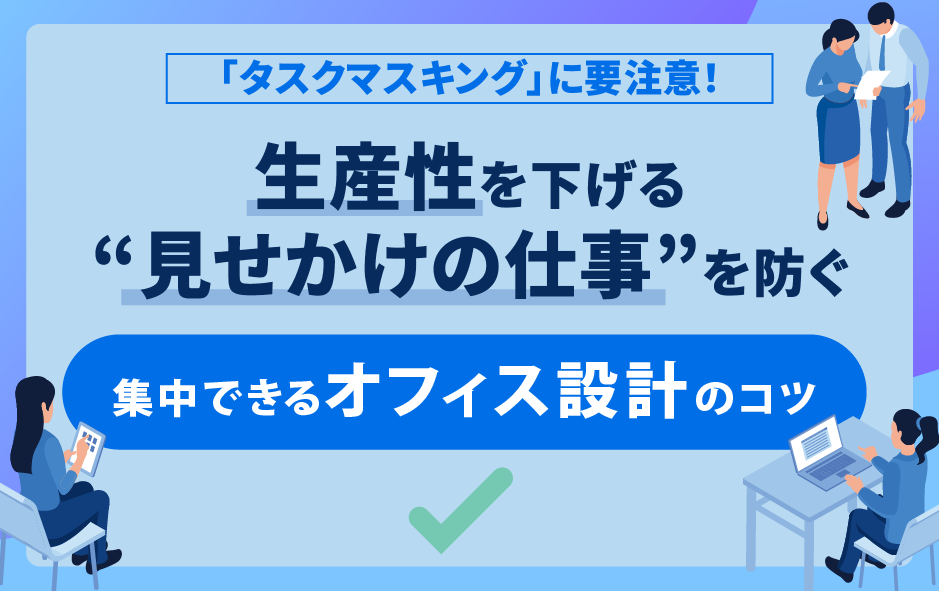
「オフィスにいるとなぜか集中できず、つい他の作業に手をつけてしまう…」その現象は、無意識に生産性を蝕む「タスクマスキング」かもしれません。本記事では、近年注目されるタスクマスキングが起こる根本的な原因をオフィス環境から解き明かし、生産性を最大化するための具体的なオフィス設計のアプローチを解説します。
集中と協業を両立させる、これからの働き方のヒントを提供します。
オフィスに潜む「タスクマスキング」とは? いま注目の理由
従業員の生産性が伸び悩む背景には、個人の能力や意欲だけでは片付けられない、根深い問題が存在します。
その一つが、無意識のうちに集中を妨げる「タスクマスキング」です。ハイブリッドワークが普及し、オフィスの役割が問い直される今、この課題への向き合い方が、企業の競争力を左右するかもしれません。
一見仕事をしているようでも生産性は低下?「タスクマスキング」とは
本来取り組むべき重要なタスクがあるにもかかわらず、無意識にメールチェックや簡単な資料整理といった別の作業を始めてしまう。この一見、仕事をしているように見せかけてしまう行動が「タスクマスキング」です。
本質的な業務から注意が逸れることで、脳には不要な負荷がかかり、集中力は散漫になります。
結果として、一つひとつの業務品質が下がるだけでなく、プロジェクト全体の遅延にも繋がりかねない、静かに生産性を蝕む深刻な問題なのです。
オフィス回帰で見えてきた?集中環境への新たな課題
新型コロナウイルス感染症の拡大を機にリモートワークが普及しましたが、その後、多くの企業でオフィスへの回帰が進んでいます。この変化の中で、改めてオフィス環境における「集中」の重要性や難しさが浮き彫りになってきました。自宅など、ある程度コントロールされた環境での作業に慣れた人々にとって、オープンなオフィス空間特有の雑音や視線、頻繁な割り込みは、以前にも増して集中力を削ぐ要因となり得ます。
実際に、株式会社ロッテの調査では、約8割のデスクワーカーがオフィスで集中できないと感じており、半数以上がコロナ禍を経て集中するのが下手になったと回答(※1)。このような状況は、従業員が意図せずタスクマスキングに走ってしまう一因ともなり得ます。
オフィスにおけるタスクマスキング発生のメカニズム

「タスクマスキングとは何か」を理解した次のステップは、それがなぜオフィス環境で頻繁に発生するのかという“構造的な背景”を知ることです。ここでは、オフィス特有の空間的・心理的要因がどのように従業員の行動に影響を与え、無意識のうちに「見せかけの仕事」へと導いてしまうのか、そのメカニズムを紐解きます。
周囲の視線が「見せかけの仕事」を生む
人間は社会的な生き物であり、他者の存在を常に意識しています。オフィスという環境において、周囲からの視線や音、人の気配は、時に過度なプレッシャーやストレスの原因となります。特に、評価を気にするあまり、「常に忙しくしている姿を見せなければならない」という強迫観念に駆られる人も少なくありません。
このような心理状態では、集中が途切れた際に正直に休憩を取ったり、じっくりと考え事をしたりする余裕が失われがちです。その結果、手持ち無沙汰に見えないようにとりあえずメールを何度も確認する、ウェブサイトを漫然と眺める、といったタスクマスキング行動に繋がりやすくなります。
つまり、周囲の刺激が、本質的でない「見せるための作業」を誘発してしまうのです。
画一的なオフィスが招く、個々の業務特性とのミスマッチ
多くの企業で採用されている画一的なオフィスレイアウトは、管理効率の面ではメリットがあるかもしれませんが、従業員一人ひとりの業務特性に対応しきれないという側面があります。
例えば、深い集中と思考を要するプログラミングや企画立案といった業務と、頻繁なコミュニケーションやチームでの協調作業が求められる業務とでは、理想的な作業環境は全く異なります。
このような異なるニーズが混在するにもかかわらず、空間が一律であると、「どの業務にも最適ではない中途半端な空間」で過ごすことを強いられます。結果として、集中がうまくできない → 仕事が進まない → それでも周囲に“働いている姿”を見せる必要がある → タスクマスキングに逃げ込む、という悪循環に陥ってしまうのです。
個人の意識の問題と諦める前に。解決の鍵は「オフィス設計」にあり
タスクマスキングの原因を「集中できないのは本人の意識が低いからだ」と結論づけるのは早計です。
多くの場合、その原因は個人の資質ではなく、働く環境そのものに潜んでいます。人間の集中力がいかに繊細で、周囲の環境から影響を受けやすいかを理解することが、問題解決の第一歩となります。
集中を妨げる要因を物理的に排除し、業務に没頭できる環境を意図的に作り出すアプローチ。それこそが、本質的な生産性向上につながる「オフィス設計」という視点です。
生産性を奪う3つの要因とは?集中力低下を誘発するオフィス環境

タスクマスキングの根本的な要因のひとつは、オフィス環境が人間の認知機能に与える影響にあります。
特に「音」「視覚」「割り込み」といった外部からの刺激は、集中力を分断し、深い思考に没頭することを難しくします。ここでは、こうした“3つのノイズ”が生産性をどう奪うのかを、要因別に具体的に見ていきましょう。
集中を遮る「音のノイズ」:周囲の会話、通知音、環境音
オフィスにおける生産性低下の最大の要因とも言えるのが、コントロール不能な音です。
ある調査では、オフィスワーカーが仕事中に最も不快に感じる騒音源として「周りの会話や作業音」がトップに挙げられています(※2)。自分に関係のない会話や通知音が、いかに思考の継続を困難にさせているかがうかがえます。
注意を散らす「視覚のノイズ」:人の往来や雑然とした空間
頻繁な人の往来が視界に入ったり、整理されていないデスク周りや書類の山が目に入ったりすることも、集中力を削ぐ大きな要因です。人間の脳は、視野の中の動きを無意識に追ってしまう性質を持っています。そのため、人の動きが活発なエリアでは、集中力を維持するためにより多くの精神的エネルギーを消費してしまいます。
静かな環境であっても、視覚的な情報量が過剰な空間は、それ自体が集中力の散逸を招くノイズとなり得るのです。
思考を中断させる「割り込み」:予期せぬ声かけや偶発的なコミュニケーション
コラボレーションの活性化を目指すオープンなオフィスでは、偶発的なコミュニケーションが生まれやすい一方で、それが深い集中を必要とする業務の妨げになるという側面も持ち合わせます。
予期せぬ声かけやちょっとした相談による「割り込み」は、たとえ短い時間であっても、一度中断された思考のフローを元に戻すのに、その数倍の時間とエネルギーを要すると言われています。この積み重ねが、1日の生産性を大きく損なう結果を招くのです。
タスクマスキングを防ぎ、真の集中を生み出すための5つのオフィス設計戦略

ここまで見てきたように、タスクマスキングの背景には、集中を阻害する物理的・心理的要因が複雑に絡み合っています。では、どのように環境を設計すれば、従業員が本来の力を発揮できる“集中できるオフィス”を実現できるのでしょうか?ここでは、その戦略を考えるための5つのポイントをご紹介します。
ポイント1:作業内容に合わせて最適な環境を選べる「ABW」の考え方
ABW(Activity Based Working)とは、従業員がその時々の業務内容や目的に応じて、最も生産性の高まる場所や環境を自律的に選択できる働き方、およびその考え方です。例えば、集中して企画書を作成する際は静かな個人ブース、チームでアイデアを出し合う際は開放的なコラボレーションスペース、といった具合です。
このABWの考え方をオフィス設計に取り入れることで、従業員は自身のタスクに最適な環境を選べるようになり、無理に周囲に合わせたり、集中できない環境で我慢したりする必要がなくなります。結果として、タスクマスキングのような行動を減らし、本来の業務への没入を促進する効果が期待できるのです。
ポイント2:視線をコントロールするデスク配置とパーソナルスペースの確保
周囲の視線は、集中力を妨げる大きな要因の一つです。デスクの配置を工夫し、例えば壁向きにしたり、互い違いに配置したりするだけでも、気になる視線を遮ることができます。また、高すぎず低すぎない適切な高さのパーティションを設置することで、個人のパーソナルスペースを確保し、心理的な安心感を与えることも重要です。
これらの工夫は、従業員が「見られている」というプレッシャーから解放され、自分の業務に安心して取り組むために不可欠と言えるでしょう。オフィスレイアウトを見直す際は、この視点を取り入れたいものです。
ポイント3:音環境の改善策としてのサウンドマスキングと集中ブースの導入
オフィス内の会話や電話の音、キーボードを叩く音など、さまざまな「音」も集中の妨げとなります。
これらの対策として、サウンドマスキングシステムの導入が有効です。これは、空調音のような特殊な背景音を流すことで、周囲の会話の明瞭度を下げ、気になる音をカモフラージュする技術です。
さらに、完全に音を遮断できる集中ブースやソロワークスペースを設けることも効果的です。重要な作業やオンライン会議など、特に高い集中力が求められる場面で活用することで、業務効率の向上が期待できます。静かな環境は、タスクマスキングに頼らずとも深い思考を可能にするのです。
ポイント4:五感を刺激し心地よさを生む照明計画とバイオフィリックデザイン
快適なオフィス環境は、従業員の心理状態にも大きく影響します。例えば、自然光を多く取り入れたり、時間帯や作業内容に合わせて照度や色温度を調整できる照明システムを導入したりすることは、集中力の維持や疲労軽減に繋がります。人間の生体リズムに合わせた照明計画は、ウェルビーイングの観点からも重要です。
また、近年注目されているのがバイオフィリックデザインです。これは、観葉植物を配置したり、木目調の素材を取り入れたり、窓から自然の景色が見えるようにしたりと、オフィス空間に自然の要素を取り込むデザイン手法です。
心地よい環境はタスクマスキングのような逃避行動を減らす一助となるでしょう。
ポイント5:業務特性に応じたゾーニングと多様なワークスペースの提供
従業員の業務内容は一つではありません。集中して行う個人作業、活発な議論が求められるチーム作業、機密性の高い情報を扱う作業など、その特性は多岐にわたります。オフィス全体を画一的な空間にするのではなく、これらの業務特性に応じてエリアを分ける「ゾーニング」が重要です。
例えば、静かに集中するための「フォーカスゾーン」、チームで集まりやすい「コラボレーションゾーン」、リラックスや雑談に適した「リフレッシュゾーン」、機密情報を扱うための「プライベートゾーン」などを設けることで、従業員はタスクに最適な場所を選べます。このような多様な選択肢が、従業員エンゲージメントを高め、タスクマスキングの必要性を減らしていくのです。オフィスレイアウト計画の初期段階から検討すべきポイントと言えます。
まとめ
本記事では、オフィスにおける「タスクマスキング」の問題点と、その背景にあるオフィス環境の課題について掘り下げてきました。
タスクマスキングは、個人の問題として片付けられるものではなく、多くの場合、働き方や働く環境に起因しています。従業員一人ひとりが活き活きと働き、その能力を最大限に発揮できるオフィス環境は、企業の持続的な成長にとって不可欠な投資と言えるでしょう。この記事が、皆様のオフィス改善の一助となれば幸いです。
出典
※1/株式会社ロッテ:全国一斉オフィス集中調査
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000064.000110734.html
※2/大建工業株式外社:【第3回】オフィスに出社する会社員116名に聞いた「オフィス内における音環境の問題点」
https://www.daiken.jp/buildingmaterials/publicnews/article/office_research022b.html

